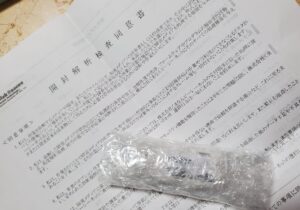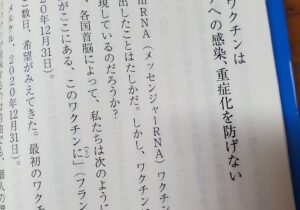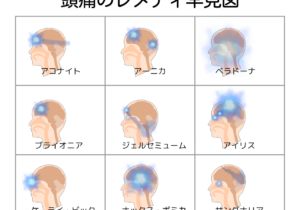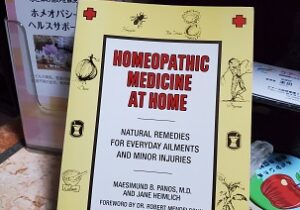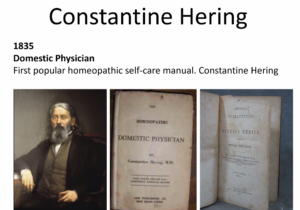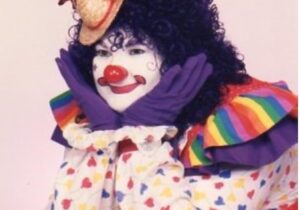For your health
保健師による
健康相談サロン
concept
子供6人を育てる
育てママが運営する
健康相談サロン
自然療法を用いた、自然治癒力、自己調整力を
有効活用することで
こころとからだの健康を支援します。
ホームレメディでは副作用の心配がない
「ホメオパシー療法」を使用し様々な健康問題に
対応しています。

profile

ホームレメディくまもと
代表 末田三紀子
保有資格
看護師 保健師 養護教諭第一種
ホメオパス(ホメオパシー療法士)
アニマルホメオパス
経歴
1994年~
広島県立広島病院(看護師)
2000年~
(財)社会保険健康事業財団大阪府支部(保健師)
2008年
RAH(現 ホメオパシー統合医療専門学校)卒業
ホメオパス、アニマルホメオパスとして登録
2009年~
ホメオパシーセンター開設
2015年~
私立高校看護科 教員および臨床実習指導者
こんなお悩みありませんか?
- 問題行動、精神的な問題を抱えている方
- 効果的な治療法がなく困っている方
- 従来の治療法の副作用が不安な方
- 生活の質を考えたい場合
- 長期的な健康を望んでいる方
赤ちゃんからお年寄り、
妊婦さんまでどなたでも相談できます
ホームレメディーの
健康相談♪
看護師や保健師といった医療専門のスキルを習得し、国家資格を所有しているカウンセラーが対応します。
-
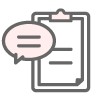
健康相談
-

出産・子育て
-
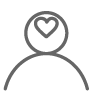
発達障害
-
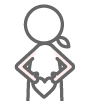
女性の悩み
-

アレルギー
-

アニマル
column